週刊新潮「いのちの『食』訪問」
「いのちの『食』訪問」 山中の美味・猪鍋
◇週刊新潮 塩田丸男さん執筆
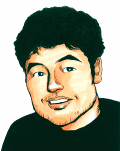 2000年5月から週刊新潮に、塩田丸男さんが、『いのちの「食」訪問』を連載されていました。2002年10月に、スズキヤを訪問。遠山の猪肉は当然だけど、我店がふさわしいかとも思いましたが、猟師さんと共に、貴重な時間を過ごせました。塩田先生は、その時は79歳でしたが、 とてもオチャメな方。スズキヤのホームページが気に入って、取材を決めてくれたそうです。
2000年5月から週刊新潮に、塩田丸男さんが、『いのちの「食」訪問』を連載されていました。2002年10月に、スズキヤを訪問。遠山の猪肉は当然だけど、我店がふさわしいかとも思いましたが、猟師さんと共に、貴重な時間を過ごせました。塩田先生は、その時は79歳でしたが、 とてもオチャメな方。スズキヤのホームページが気に入って、取材を決めてくれたそうです。
by 若旦那

※当時の原文のままなので、現在の表記と異なる部分があります。
タァーン!タァーン! 晩秋の南アルプス山麓”遠山郷”に猪を撃つ銃声がこだました。
ここ遠山郷では古くから猪・鹿・熊の大物3種が獲られ、貴重な蛋白源として山峡の人々を支えて来たのだ。
今も猪を撃つベテラン猟師と、深山の獣肉を美味しく提供している『スズキヤ肉店』を訪問した。
 猪が山に残した”獣道”を追いながら、ベテラン猟師は、「罠」を仕掛けていく。細い糸で拵えた仕掛けに枯葉を被せると、人間の眼にも罠とは分からない。後 は罠に繋った猪を撃ってとどめをさす・・・・。日本の山から狼が絶滅して以来、猪・鹿は増えすぎ、山峡の農家や林家に大被害をもたらす”害獣”となった。 それ故に猟師たちは猟期以外でも猪を撃つのである。こうして獲れた「野生の猪肉」は、野趣あふれる深山の味として販売され、スポーツマンや武道家の間で は、ことに人気が高いという。家畜の肉にはない天然エキスが身体に響くというのである。
猪が山に残した”獣道”を追いながら、ベテラン猟師は、「罠」を仕掛けていく。細い糸で拵えた仕掛けに枯葉を被せると、人間の眼にも罠とは分からない。後 は罠に繋った猪を撃ってとどめをさす・・・・。日本の山から狼が絶滅して以来、猪・鹿は増えすぎ、山峡の農家や林家に大被害をもたらす”害獣”となった。 それ故に猟師たちは猟期以外でも猪を撃つのである。こうして獲れた「野生の猪肉」は、野趣あふれる深山の味として販売され、スポーツマンや武道家の間で は、ことに人気が高いという。家畜の肉にはない天然エキスが身体に響くというのである。
カラーグラビアの、山中に横たわる二頭の猪(いのしし)の写真には驚かれた読者も多いのではないだろうか。
大きいほうが雌で、四歳か五歳。
内蔵を取り除いた後で計算したら四十キロあった。小さいほうは三歳くらいの若い雄猪で三十三キロ。
猪は大きいのだと百キロを超えるのもあるから、この二頭はそれほど大きい猪のではないのだが、間近に見るその姿はかなりの迫力があった。
編集部のWさんは、猪を食べるのも今回が初めてとのことで、ほんものの猪に触れるのはもちろん生まれて初めてだからかなり緊張していた。
猟師の遠山恒(ひさし)さんと鎌倉正良(まさなが)さんは何本かの銃を携行していた。
久しぶりに銃を手にして、軍隊時代を思い出した私が立射の姿勢で銃を構えて見せたら、Wさんはびっくりして、
「撃たないでくださいよ、猪じゃないんだから」
とパッと飛びのいた。
今回のテーマは猪。
「薬食い」という言葉があるが、これは、古来、獣肉食を忌避した日本人が獣肉を食べるに当たって、
「私は汚らわしい獣肉を食べたくはないのだが、今健康を損ねているので、回復のために薬としてたべるのだ。これは獣肉ではないのだよ、薬なんだよ。薬。薬」
と自分にも人にも言い訳したごまかしの言葉である。
 スペインでは紀元前一万二千年頃の猪の壁画が発見されているが、日本でも、猪はきわめて古くから食べられてきた動物である。
スペインでは紀元前一万二千年頃の猪の壁画が発見されているが、日本でも、猪はきわめて古くから食べられてきた動物である。
それでもいまだに家畜化されず野生動物として跳梁し、捕獲されて食べられている。日本人とっては、深い、また、不思議な縁のある動物といわなければならない。
猪は寒いところが苦手のようで、北海道や東北地方には棲息していない。”名産地”とされるのは広島県の安芸、三重県の伊勢、神奈川県の丹沢などだが、最も有名なのは、第124回「松茸」で訪問した兵庫県の丹波篠山(たんばささやま)である。
この地方の民謡「デカンショ節」にも、
雪がチラチラ丹沢の宿に猪が飛び込む牡丹鍋(ぼたんなべ)
という文句がある。
牡丹鍋というのは猪鍋(ししなべ)のことだ。馬肉鍋を桜鍋(さくらなべ)というのと同じような美称である。「牡丹に唐獅子(からじし)」にちなんだものだろう。
牡丹鍋は広く知られ、用いられている言葉だが、
「うちでは<ししなべ>と言っています。おためごかしの美称は使いません。猪の鍋は<ししなべ>にきまってるじゃありませんか」
と強情なことを言っている店がある。長野県下伊那郡南信濃(みなみしなの)村和田の「スズキヤ」という店だ。
『なんでも食べるゾ信州人』(中田敬三著)という、お国自慢話がいっぱい書いてある本がある。その中に、猪鍋は下伊那の遠山(とおやま)地方のものが一番うまいと書いてある。
遠山は「スズキヤ」のある南信濃村の旧名である。「南信濃村発足四十周年記念村勢要覧」には、
「明治八年に上村、木沢村、和田村、八重河内村が統合され遠山村になりましたが、合併・分離の歴史を辿り、昭和三十五年に現在の南信濃村が誕生しました」
とある。この村勢要覧で私が目を丸くしたのは、
「村人は転げ落ちそうな急斜面で百姓をし」
という一行だ。こんなことを書いている村勢要覧も町勢要覧も聞いたことがない。
どんな村なのだろう。また、そういうところの猪鍋が本に書かれるほどうまい、というのはどういうわけなのだろう、と私は興味を持った。そして、今回の訪問先を遠山郷南信濃村にきめたのだ。
「村勢要覧」には、
「海抜は350~3013m、森林面積96.7%、経営耕地面積0.5%の山村」
とあったから覚悟はしていたが、行ってみると想像以上の山奥の村だった。
「スズキヤ」は村を貫く国道152号沿いにあった。
国道沿い、というと聞こえはいいが、この国道152号は私がこれまで通った国道の中ではもっともお粗末な国道だった。
軽自動車もすれ違えない狭いトンネルがあって交互通行の信号機が設置してあったりする。
「国道152号を改良補修せよ」という立て看板がいくつも立てられていた。
たしかに、猪がいっぱいいそうな山々が連なっていた。
『イノシシと人間-共に生きる』という本がある。著者の高橋春成(しゅんじょう)さんは生物地理が専門の文学博士で、奈良大学の教授。
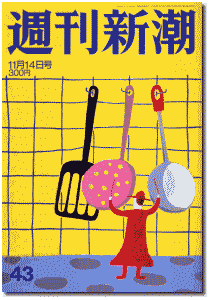 この本の「まえがき」でも、
この本の「まえがき」でも、
「イノシシ」ほど、古くから、良くも悪くも、人間と共に生きてきた動物はいないであろう。イノシシの肉は獣の中で最も美味であり、古くから各地で食用肉に狩猟されてきた」
と猪肉の美味が強調されている。
日本人が稲作を始めたのは縄文(じょうもん)末期からのことで、それまでは、どんぐりが主食だった。イノシシの主食もどんぐりだから、われわれの祖先は猪とどんぐりを奪い合うという競合関係で生きてきた。
日本人は米との付き合いより猪との付き合いのほうが長いのだ、というようなことも書かれている。
現代では、猪は人間が汗水流して作った畑の作物を奪って食べ、人間は猪そのものを捕まえて食う、という敵対関係だが、人間のほうが優勢だとは必ずしもいえないらしい。
現在、日本人はどれくらい猪を食べているのだろうか。
私が新聞社に勤めていた昭和三十年代には、新宿にも新橋にも猪料理の専門店があって繁盛していた。私も冬場には時々足を運んだ。
「<シシ食った報い>というのは、悪事を働いたために報いを受ける、という意味に解釈されているが、ほんとうは<猪食ったら温(ぬく)い>なんだ。猪鍋を 食うとほんとうに体が温まるからね」
と先輩から講釈されたのもそうした店でであった。今はそんな専門店も姿を消した。昔に比べると、猪を食べる人はかなり少なくなっているのではないのだろうか。
猪肉の値段なんかもご存じない方のほうが多いだろうからちょっとご紹介しておこう。「スズキヤ」 での小売価格である。
野生の猪上肉・・・・・・100グラム 700円
子猪の肉・・・・・・・・・・100グラム 850円
極上の猪肉・・・・・・・・100グラム 850円
猪肉ソーセージ・・・・1本 600円
猪の味噌漬け・・・・・・200グラム 600円
といった按配である。昔より安くなったような気がする。
ちなみに私が女房のお供をして時々ショッピングに行くスーパーの紀伊国屋では牛肉が普通の肉で100グラム当たり八百円から千二百円、上等なのになると三千円から五千円以上もしている。
それでも「スズキヤ」は経営状態のよさそうな元気な店だった。
「ほとんどが県外のお客です。浜松とか名古屋とか各地から来られます。東京からも。こんな辺鄙なところへわざわざ来られる。ありがたいことです」
と店主の鈴木理孔(まさよし)さんはいう。
 南信濃村は昭和二十五年には六千五百人あった人口が、年々減って今は二千三百人。「スズキヤ」のあるあたりは村のメインストリートなのだが、軒の傾いた家もちらほらあって過疎の気分が濃い。
南信濃村は昭和二十五年には六千五百人あった人口が、年々減って今は二千三百人。「スズキヤ」のあるあたりは村のメインストリートなのだが、軒の傾いた家もちらほらあって過疎の気分が濃い。
そんな中で、明るいベージュ色の外壁で三階建ての「スズキヤ」の店舗はひときわ目立っていた。
今年七十二歳になる鈴木さんはこの村で生まれ育った人だが、家業は肉屋ではない。この店を始めたのは奥さんの智惠子さんのアドバイスによるものだった。結婚前は、鈴木さんは製材所に勤めて鋸の目立てをしていた。
昭和三十年に猪肉屋を開店したが、二十坪足らずの小さな平屋の店だった。今は、猪のほか熊(くま)、鹿、兎(うさぎ)、山羊(やぎ)、雉(きじ)、仔羊(ラム)など他品目の営業をしている。
猪は人気が出たので、近年は養殖猪も出回っているが、「スズキヤ」では村の猟師何人かと契約して、野生の猪や鹿を捕獲して用いているのだそうだ。
カラーグラビアの猪も、その契約猟師の中の古参格である遠山恒さんと鎌倉正良さんのお二人が、私たちが訪問する前日に山に入って捕獲してきたものなのであ る。
そのお二人に山に案内してもらって話を聞いた。
猪の猟期は毎年、十一月十五日から翌年の二月十五日までの三か月間。
一日に一頭か二頭、獲れればいいほうで、これまでに一日五頭獲ったのが最高だとのこと。
「スズキヤ」は景気がよさそうだったが、猟師さんは必ずしもそうではない様子だった。
「昔、といっても十二、三年前のことだが、一貫目千五百円くらいで買うてもろうとった。今は安うなって一貫目千円だ」
と遠山さんは額の皺を深めて言う。
価格が下がっただけではない。
「昔はスズキヤの旦那が頭を下げてわしらのところに肉を取りに来たものだった。値段もわしらがきめた。今はわしらが頭を下げて肉をスズキヤに運んでいく。値段もスズキヤがきめる」
のだそうで、猟師の力が昔に比べると弱くなった、という社会的な地位の変動がうかがえる。それが猪と人間の関係にも影響を与えている。
近年、猪害が拡大しているといわれている。 私もこの連載の訪問先で、これまでに何度も猪害のひどさを聞かされた。
北九州市合馬の筍(たけのこ)山を見に行った時は、筍山の周囲に鉄条網と電線が張り巡らしてあるのに驚いた。
電線をまたいで中へ入ろうとした私を筍山の主はあわてて押しとどめ、
「強い電流が通っていますから」
と スイッチを切った。天城(あまぎ)の山葵(わさび)田にも鉄条網が張りめぐらされていた。
「猪が山葵を食うのですか」と尋ねたら、「いや、山葵は食べませんがね。山葵をほじくり返して、その下にいる蚯蚓(みみず)や沢蟹(さわがに)を食べるのですよ」とのことだった。
猪と人間との戦いの歴史は何千年にものぼるだろう。猪なんかに人間が負けるはずがない、と思いたいが、どうもそうでもないらしい。
『イノシシと人間』にも、
「現在イノシシは分布域を拡大させており、農作物被害の発生量も急増している。(中略)日本の農業とイノシシの戦いが激化していくことが予想される」
と述べられている。
昔は南信濃村だけで、猟師は百人以上いた。それが今では、登録されてるのは七十人くらいはいるが、実際に鉄砲を持って猟をしていのは三十人いるかいないかだ、とのことだ。全国的な統計を見ても、昭和四十五年には五十三万人いた狩猟者が昭和六十年には三十八万人。平成十一年には十六万人と急激に現象している。今後とも増える予測はない。
「誰も猟師なんかになりたがらん。うちの息子ももう五十近いが、郵便局に勤めておって、鉄砲撃つ気はさらさらない。うちは、親子代々、ずっと猟師だったが、猟師はわしでおしまいだよ」
と遠山さんは苦笑した。
鎌倉さんも同様で、三十四歳になる息子さんはサラリーマンで、親の仕事を受け継ぐつもりはまったくないそうだ。
つらい仕事だし、その割合には報酬は多くないし、猟師になり手がないのも仕方のないことだ、と遠山さんも鎌倉さんもとっくに観念しているようであった。
“猪事情”が大変面白かったので、料理の話が最後になってしまったが、「スズキヤ」で、さまざまな猪料理をたっぷりご馳走になったことはいうまでもない。
料理を作ってくださったのは奥さんの智惠子さんだが、采配をふるってくださったのは、ご長男の理(まさし)さんだ。
名著『飲食事典』(本山萩舟(てきしゅう)著)にも、
「原則として獣肉は焼いて食うのが最もうまく、猪肉も脂肪の少ないところを薄切りにし、10分間くらい生姜醤油につけてから焼鍋か金網にでものせて焼く」のが一番だ、とあるが理さんが私たちに、
「これが一番です」
と真っ先に勧めてくれたのは、猪のヒレ肉のカツだった。
ヒレは、背骨の内側の左右にある脂の少ない部分で牛や豚でも最上等の部位とされ、価格も高い。
「一頭から五、六百グラムくらいしかとれませんからね。店で小売りはしないのです」
といって理さんが差し出したカツを真っ先に頬張って「うまい!」と叫んだのはWさんだった。
生まれて初めての猪肉食いで、プロが一押しするものを試したのだから賛嘆するのも当然だろう。
 「獣肉は焼くのが一番」とする『飲食事典』と猪は唐揚げが一番という「スズキヤ」の”若旦那”(理さんはホームページでこう自称している)とどちらに軍配をあげたらいいのだろう。
「獣肉は焼くのが一番」とする『飲食事典』と猪は唐揚げが一番という「スズキヤ」の”若旦那”(理さんはホームページでこう自称している)とどちらに軍配をあげたらいいのだろう。
猪鍋も頂戴した。これも”若旦那”は、
「山の肉は焼いてもいいんだけれど、酒と水で一時間くらい煮込んだほうがずっと旨味が出るんですよ。野菜にも風味が付きますしね」
と『飲食事典』に逆らっている。
猪鍋の味付けは信州味噌でする。最初に味噌をたっぷりとき、仕上げにまたちょっと入れる。味醂や砂糖を足すとどっしりした味になる。
そんなアドバイスも”若旦那”はしてくれた。
猪鍋はこれまでに何十回と食べているが、すべて料理店のものばかりだ。この冬は、ひとつ”若旦那”直伝の猪鍋を自前でやってみるか、と空想しながらこの一文を擱筆、じゃなかった打ち納めすることにしよう。







